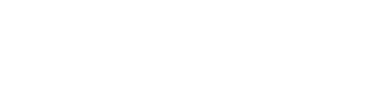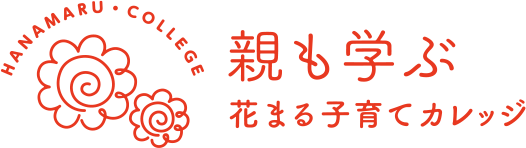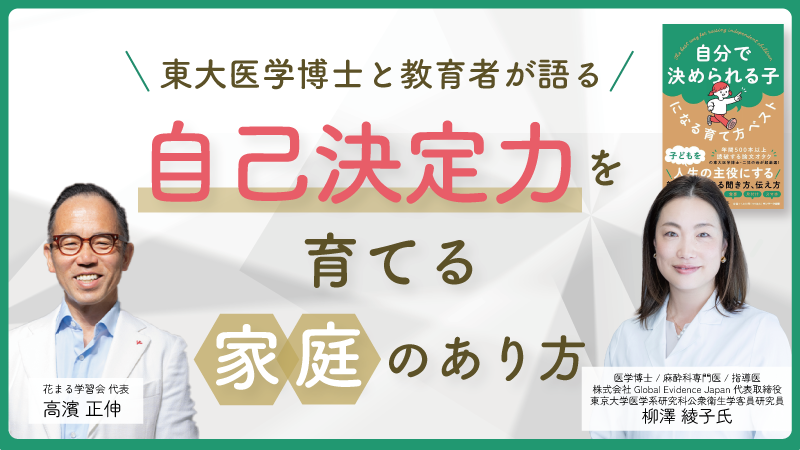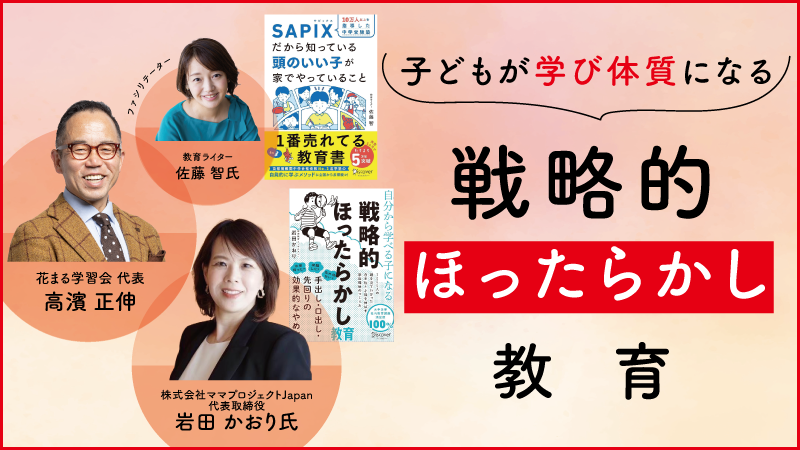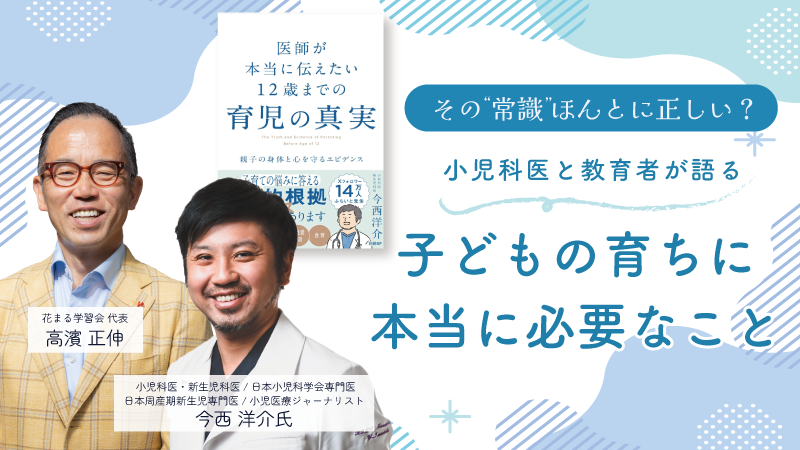近年、子どもの「あと伸び力(将来的な伸びしろ)」を支えるカギとして注目されているのが、「非認知能力」です。
学力や知識といった“見える力”に対して、自己肯定感や自制心、共感力、創造性、やり抜く力といった“見えにくいけれど一生を支える力”——これらが、今、急速に注目を集めています。
では、そうした非認知能力はどのように育まれるのでしょうか?
その答えのひとつが、「幼児期にたっぷり遊ぶこと」です。
自由な発想で思いきり“遊び込む”体験は、子どもにとっての最良の学び。
失敗を恐れず挑戦する心、自分の気持ちを言葉にする力、友達との関わりの中で育まれる協調性……。
まさに非認知能力の源が、遊びの中に詰まっています。
今回の対談では、非認知能力とは何か?なぜ今それが求められているのか?という視点に加え、
● ご家庭で親がどのように子どもに関われるか
● 遊びや対話の中で非認知能力をどう育てるか
● 日常で実践できる関わり方や声かけのヒント
といった具体的な方法についても、保護者の皆さまに寄り添いながらご紹介します。
さらに、本対談では「親子が共に育つ」ことの大切さにも焦点を当てます。
家庭の中での教育環境を整えることは、子どもだけでなく親自身の安心や学びにもつながります。
登壇者プロフィール
=========================
江藤 真規氏(えとう まき)
サイタコーチングスクール/クロワール幼児教室 主宰
アカデミックコーチング学会 理事/公益財団法人 民際センター評議員/一般財団法人教育振興財団 理事
東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。2人の娘の子育て経験を通して、親子間のコミュニケーションの重要性を実感、コーチングの認定資格を取得。現在、教育コーチングオフィス、サイタコーディネーション代表として、保護者、教職員を対象とした講演・セミナー、執筆活動などを行う。子育ての孤立化を防ぎ、よりよい子育てに向かうためには「保護者同士のつながりの場」が必要と感じ、2010年春、子育てコーチングスクール「マザーカレッジ(現サイタコーチングスクール)」を設立。子どもの主体性・思考力・表現力を育む家庭環境作り、母親の社会的役割を拡げる活動を行っている。
著書は『勉強ができる子の育て方』『合格力コーチング』(以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン)『子どもを育てる魔法の言い換え辞典』(扶桑社)『母親が知らないとツライ「女の子」の育て方』(秀和システム)など多数。
2019年度文部科学省「男女共同参画推進のための学び・キャリア形成支援事業」委員
大塚 由香(おおつか ゆか)
花まるおやこクラス発起人
4歳以下親子対象の「花まるおやこクラス」発起人。親子が遊びをとおして学びあうクラスの運営、保護者のサポートにあたっている。小学6年生と4歳の姉妹の母。子どもをメシが食える大人に育てる学習塾「花まる学習会」の教室長として幼児・小学生・中学生の指導を経験。教室長時代に出会った親子との関わりと自らの子育てをとおして、「目の前のわが子と自分の心を軸とした子育て」の大切さを痛感。母向けのワークショップ開催を経て、2020年、0歳から年少親子のためのクラス「花まるおやこクラス」を同僚2名とともに立ち上げる。50名の音楽家の生涯を描いたアノネ音楽教室の伝記教材『おぺら』を執筆。花まる学習会社員が執筆する5冊の書籍の編集に携わる。
江藤 真規氏
江藤真規氏
江藤 真規氏
江藤 真規
江藤真規
江藤 真規
大塚 由香
大塚由香
大塚 由香